2025年4月28日更新
24年以降、25年と日銀の政策金利の二度の引き上げがあり、さらなる引き上げ気運がありましたが、アメリカのトランプ大統領による、世界経済や今までの同盟関係などを完全に無視した関税政策により、世界的な混乱が起こっています。
日銀もこの様な不透明な状況下では、金利を変更することは出来ずに、様子見の状態になっています。アメリカとの関税交渉がまとまるまでは、手詰まり状態になっています。
大方の金融アナリストの予測では、本年度中に二度、程度の利上げがあるのではないかという見立てで金利は0.25%から1.0%の上昇が見込まれていたようですが、逆にアメリカとの交渉次第で、金利の上昇は無くなり、再び無金利時代に戻るという予測するアナリストもいます。
これから住宅建築をお考えの皆様は、悩ましい状況を迎えているのではないかと思いますが固定型で住宅建築をお考えの皆さまには、金利上昇前の今が建て時と言えるのかも知れません。現在は、住宅建築資材の高騰で住宅建築コストが上昇していますが、トランプ関税の影響でこの、資材上昇の流れは、そのまま持続していくような気配になっているからです。
現在ならば「子育て支援事業」に関連する補助金や「GX志向型住宅」の補助金制度など、有利な条件も選択出来るからです。
GX志向型住宅の場合は、補助金が160万円と大きいので、自社の工法で等級6以上の施工が可能な工務店であれば、6等級の追加工事も最小限で「GX思考型」住宅の補助金制度に参加できるのかも知れません。ご希望の方は松下孝建設にご相談下さい。160万円の支援金が受け取れるかも知れません。
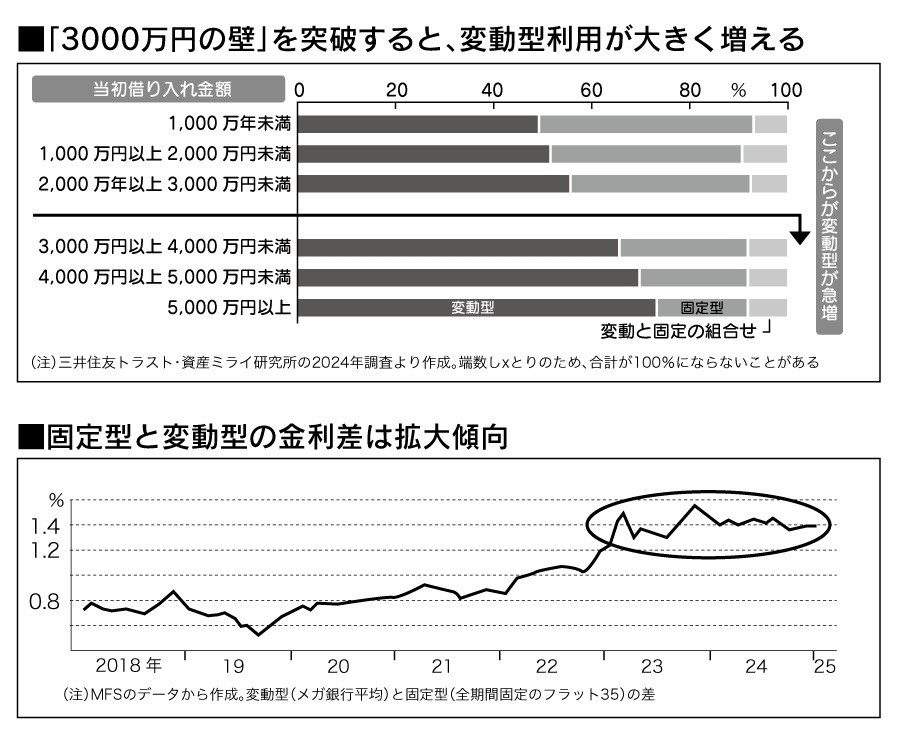
住宅ローンには、返済中に金利が変わることがある変動型と、返済中の一部期間もしくは、全期間の金利が変わらない固定型があります。変動型は市中金利と連動した金利で、市中金利が高くなると金利は上昇し、低くなると金利は低くなります。
固定型は市中金利に関係無く、契約当事の長期金利+αで設定された金利が、契約による返済期間の一部期間もしくは全期間を通して金利の変更がありません。三井住友トラスト・資産のミライ研究所の2024年の調査では、借り入れ金額が多くなるほど変動型が選ばれるのは、1000万円単位で見ると、特に「3000万円以上4000万円未満になると一気に増える傾向があり、「2000万円以上、3000万円未満」と比較して、約10ポイント高い65.3%に急上昇する様です。
一般的にローン金利は、変動型が最も低く、固定型にすると期間が長いほど高くなって行くので、足元では変動型と全期間固定型の金利は、1.4%程度と、過去約7年間で最低だった2019年9月と比較すると3倍弱に拡大しています。
借入金が大きくなれば毎月返済額も膨らむので、低い金利にして、負担を減らしたいという心理が働くから変動型にシフトするのではないかと予測されます。
将来の金利上昇リスクよりもまずは、目先の負担抑制を優先する人が増えていると予測されています。
現在の全期間、固定型金利は年1.94%「フラット35」の35年の元利均等返済で計算すると、3000万円の返済額は概ね、年100万円を突破する水準で、ちなみに2000万円なら返済額は、80万円弱にとどまります。
計算前は、金利上昇リスクを避けたいと考えていても、実際に100万円を超過するとわかれば、低金利の変動型の方が魅力的に見えても不思議はないということです。
ただ、自動車ローンなど、他にもローンを抱えている場合には、支払金額自体を少なくしたいという考え方も出て来るはずで、その辺からも3000万円の壁が生まれて来るのかもしれません。
住宅ローンの借入額が年収の何倍になるかを計算するのが年収倍率です。
一般的にローン金利の年収倍率は7倍程度までに抑えることが望ましいと言われています。年収に対して借入金額が多過ぎれば、他の生活に振り向ける支出の余裕がなくなります。もしも転職や失業などで減収に見舞われると返済も不可能になります。
国税庁の1年間、勤務した民間給与所得者の平均給与は、最新の2023年の調査で、460万円です。
この金額にローンの年収倍率の目安7倍をかけると3220万円になります。
平均的な人にとって、借入金3000万円は、年収に対する負担感が重く感じ始める境目になっているようです。
アナリストの見解は「変動型と全期間固定型の金利差は、0.7%が限度で、日銀は今後も金利上げの方向ですから今後も3000万円を越えて多く借りる場合は、変動型の利用率が高まる傾向は変わらないという見解です。
変動型の低金利で浮いた資金は、今後の金利上昇に備える必要があります。このように金融情勢の変化が激しい時期には住宅新築を考える場合も建築会社、金融機関との綿密な協力が必要です。
九州住環境研究会は、お客様の立場にたった住宅建築を目指しています。住宅のことはどんなことでもご相談下さい。
常に最良のアドバイスを用意してお待ちしています。